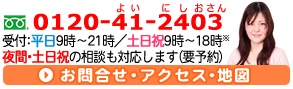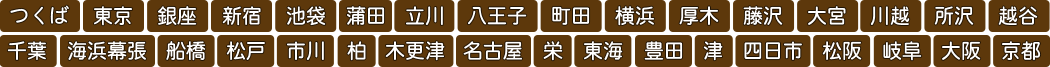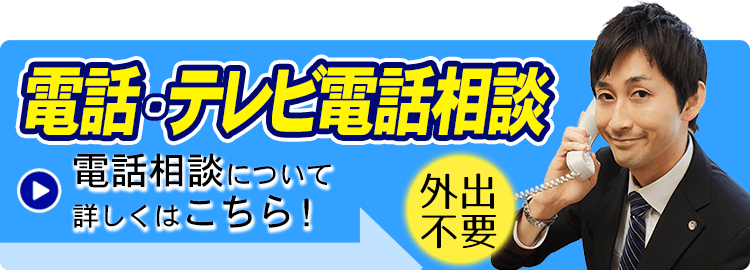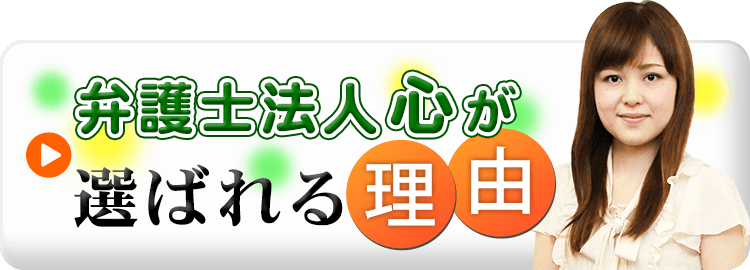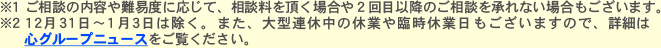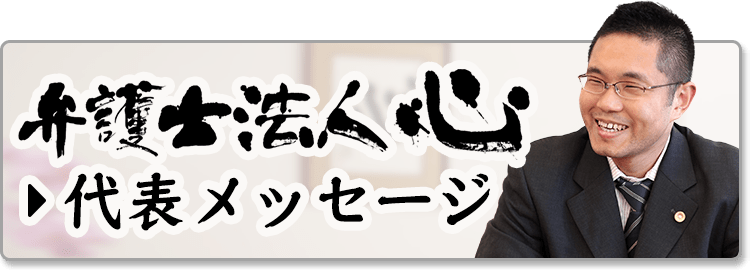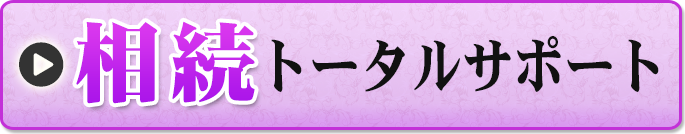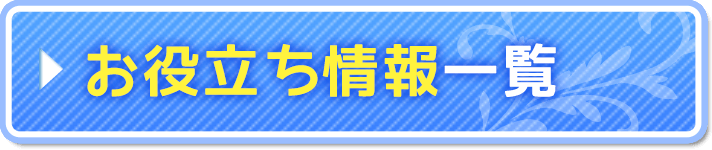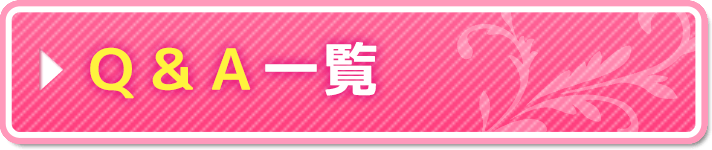遺留分の計算をする際の注意点
1 財産評価の基準時について
遺留分侵害額は、遺留分算定の基礎となる財産に、各自の遺留分を乗じることで計算されます。
遺留分算定の基礎となる財産は、おおむね、被相続人のプラスの遺産から、借金等のマイナスの遺産を差し引くことにより計算されます。
遺産が現金や預貯金の場合は、被相続人が亡くなった時点の残高がプラスの遺産として扱われることとなります。
他方、株式の場合は、刻々と値動きしますので、いつの時点の株価で評価を行うべきかが問題になります。
このように、評価が変動する財産の場合、いつの時点の評価額を用いればよいのでしょうか。
こうした評価の基準時の問題については、2019年7月に改正相続法が施行されて以降は、次のように考えることとなっています。
2 亡くなった時点が基準時になる
遺留分侵害額を算定する場合は、被相続人が亡くなった時点の評価額を用いることとなっています。
このため、被相続人が亡くなった後に遺産が値上がりしたとしても、値下がりしたとしても、遺留分侵害額の算定にあたり、考慮されません。
つまり、遺留分義務者は、遺産が値上がりした場合には、値上がりによる利益をすべて取得することができる反面、遺産が値下がりした場合には、値下がりによる損失をすべて負うこととなります。
このように、遺留分義務者は、相続後の遺産の値下がりのリスクを負うこととなってしまいます。
過去の例でも、被相続人が有していた株式について、会社が経営破綻したり、粉飾決算が発覚したりしたことにより、株価が著しく下落したことがあります。
近年でも、リーマンショックやコロナショックにより、株価が一様に大きく下落したことがありました。
このような場合には、遺留分義務者は、株式を売却したとしても、下落後の売値でしか売ることができない反面、遺留分権利者に対しては、被相続人が亡くなった時点での評価額に基づき、遺留分侵害額に相当する金銭を支払わなければならないこととなってしまいます。
このようなリスクを考えると、場合によっては、遺産を早期に売却処分して現金化し、遺留分侵害額請求に備えるのもよいかと思います。
3 遺留分についてのご相談
このように、遺留分侵害額請求がなされた場合は、どのように対応を行うべきか、慎重に判断すべき場面があります。
判断に迷うような場面では、第三者に相談するのが良いこともあるでしょう。
遺留分についてのご相談がある方につきましては、当法人までお問い合わせいただければと思います。