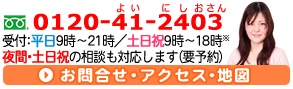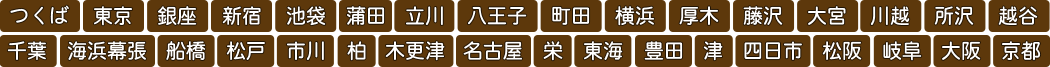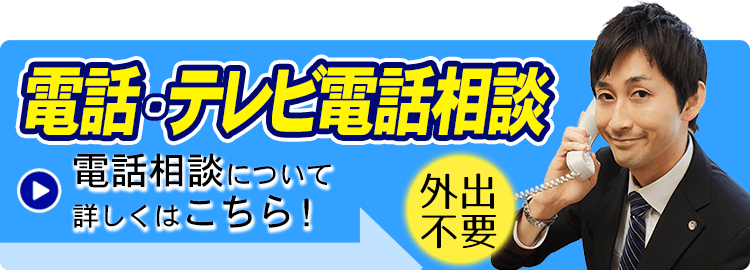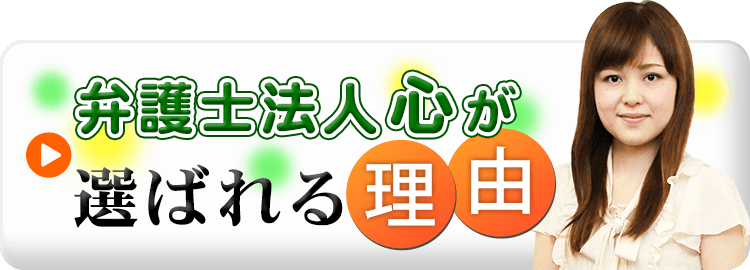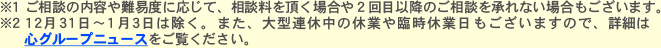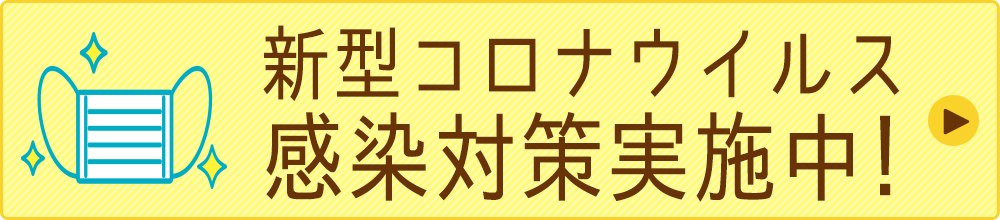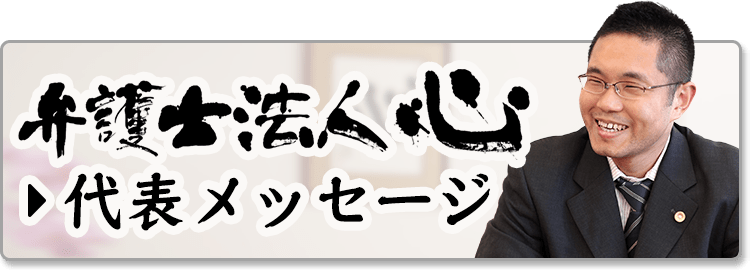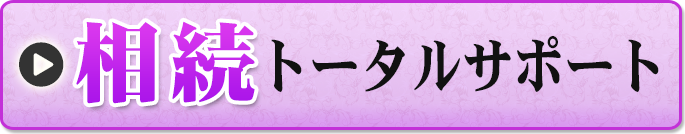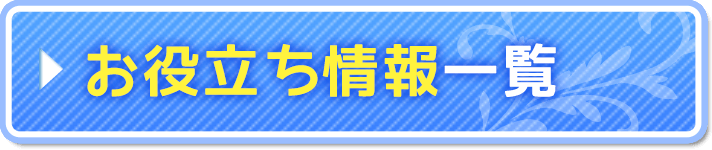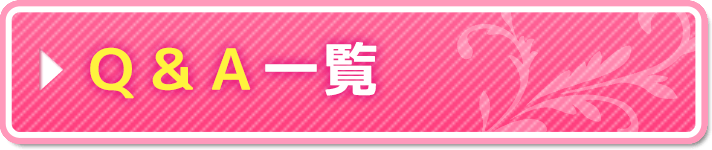遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の期限
1 法律で決められた期間
遺留分侵害額の請求をする権利については、相続関係について不安定な状態を長期化させないために、法律上、行使できる期間が限られています。
法律では、以下のように定められています(民法1048条)。
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」
2 期間が短いことに注意
まず、「1年間」という短い期間が定められていることに注意が必要です。
ただし、相続の開始(被相続人が亡くなった事実など)を知ったことのみではなく、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」も知った時から1年間です。
遺留分侵害額請求をしようと考え得るのは、自分の遺留分が他の者に侵害されていることを知っている方のみなので、このような規定になっています。
では、実際に、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時というのは、いつになるのでしょうか。
この点については法律には細かい規定はありませんが、裁判で問題になったケースについて判例があります。
判例では、「1年間の消滅時効の起算点は、単に贈与又は遺贈があったことを知るだけではなく、それが自己の遺留分を侵害し、減殺の対象になることを知った時」とされています。
ここで問題となるのは、例えば、遺言の内容が、被相続人が書くような内容でないので納得できないというような場合ですが、判例では、「遺留分権利者が減殺すべき贈与の無効を訴訟上主張していても、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されたことを認識していたときは、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者がその無効を信じているため遺留分侵害額請求権を行使しなかったことがもっともと認められる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺できることを知っていたと推認するのが相当である」とされています。
この判例は、平成30年の相続法改正前の遺留分減殺請求に関するものですが、基本的には、同改正後の遺留分侵害額請求の事案にもあてはまると考えられます。
したがって、遺留分が侵害されているのではないかと疑問を持たれた場合は、期間制限との関係で、とりあえず遺留分侵害額請求の意思表示だけでも行っておいた方がよい場合が多いですから、ご自分で判断されず、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
3 あきらめずにご相談を
遺留分侵害額を請求できる期限が過ぎてしまったのではないかとご心配な方も、相談者の方の状況によっては請求できる場合もございますので、まずは弁護士に一度ご相談ください。