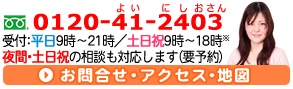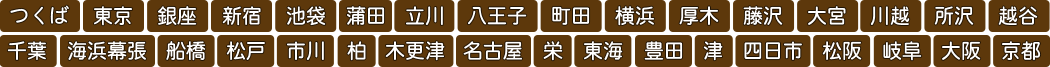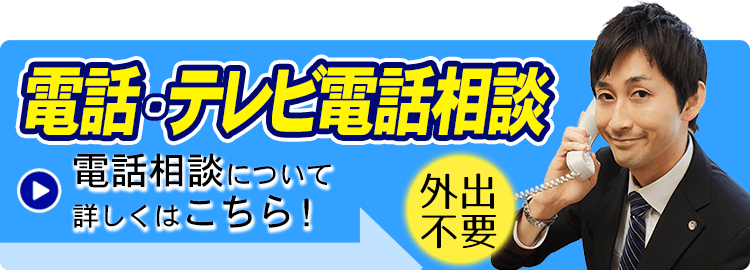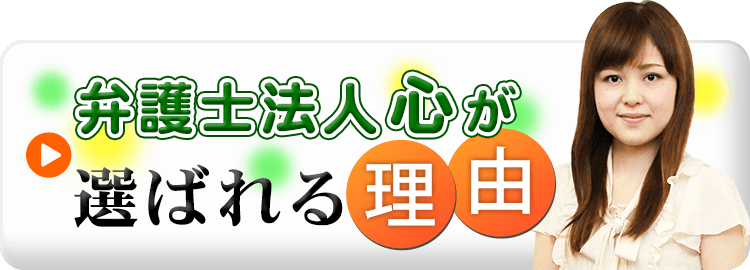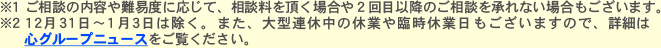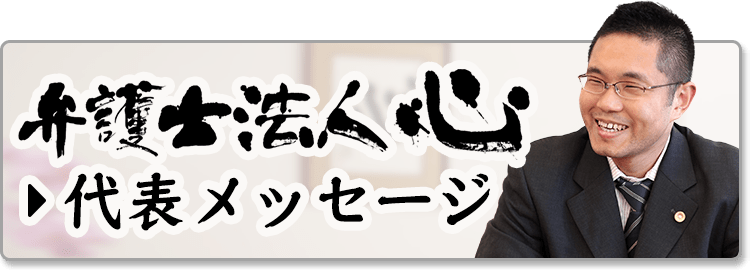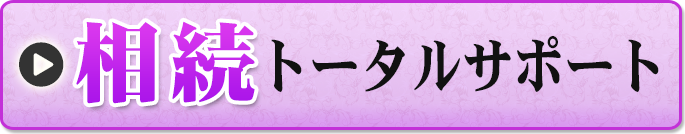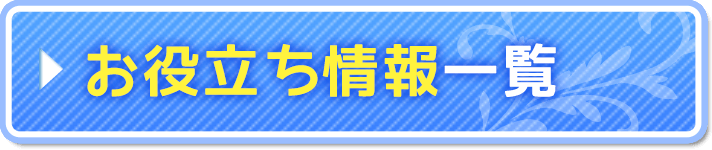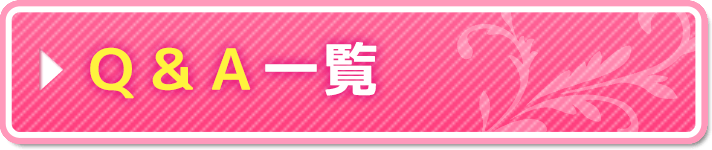遺留分に関する制度等に関するQ&A
遺留分を渡さなくて済む方法はありますか?
1 遺留分を渡さずに済むケースは限定的です
遺留分は、法律によって一定の範囲の相続人に保証された、最低限の遺産の取り分です。
基本的には、遺留分権利者から遺留分を侵害している方に対して、遺留分侵害額請求がなされた場合には、遺留分侵害額相当額の金銭を支払う必要があります。
ただし、遺留分を渡さずに済む例外的なケースはいくつか存在しますので、以下、具体的に説明します。
2 遺留分侵害額請求権が時効によって消滅している
遺留分侵害額の支払いを求める権利は、相続の開始および遺留分の侵害があったことを知った日から1年が経過すると、時効によって消滅します。
仮に遺留分侵害額の請求があったとしても、既に消滅時効が完成している場合には、消滅時効の援用をすることで、遺留分侵害額相当額の支払いをせずに済みます。
3 相続廃除がなされている・相続欠格事由がある
被相続人に対して暴力を振るっていた相続人や、被相続人に多額の借金の肩代わりをさせていた相続人などについては、被相続人が家庭裁判所に申立てをして、相続権を失わせること(相続廃除)ができる可能性があります。
相続廃除がなされた相続人は、遺留分侵害額請求ができません。
また、詐欺や脅迫によって被相続人に遺言を作成させた、または遺言の変更や撤回をさせた相続人、遺言の偽造や変造、破棄をした相続人、被相続人や他の推定相続人を死亡させた相続人は、相続権を失います(相続欠格)。
相続欠格事由がある相続人も、遺留分侵害額請求はできません。
4 生前に遺留分が放棄されている
遺留分は、被相続人がご存命のうちに放棄することが可能です。
もっとも、遺留分の放棄は遺留分権利者が自ら家庭裁判所に対して申立てをする必要があり、かつ厳しい要件を満たしていないと家庭裁判所が許可しないものと考えられます。
具体的には、生前に被相続人となる方から十分な贈与がなされているなど、最低限の取り分として保障されている遺留分を失わせても合理性を欠かないといえる事情がなければ、許可されません。