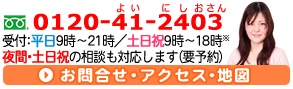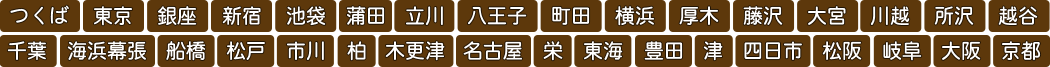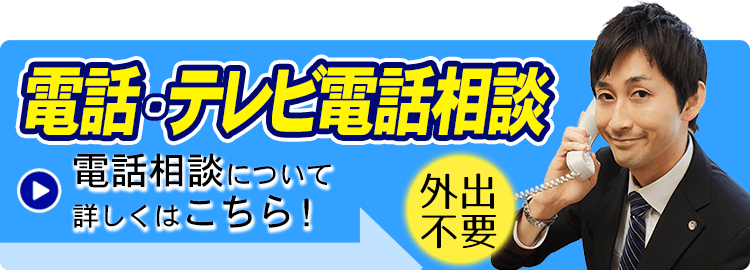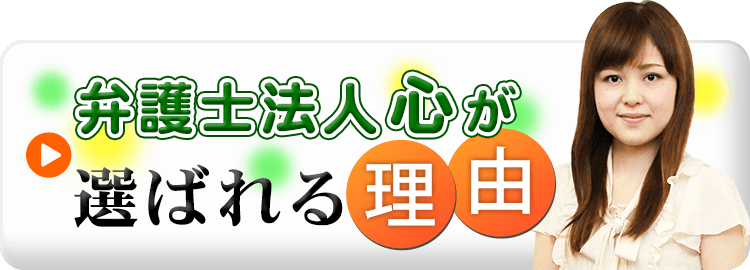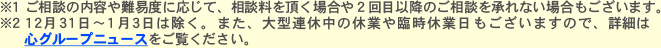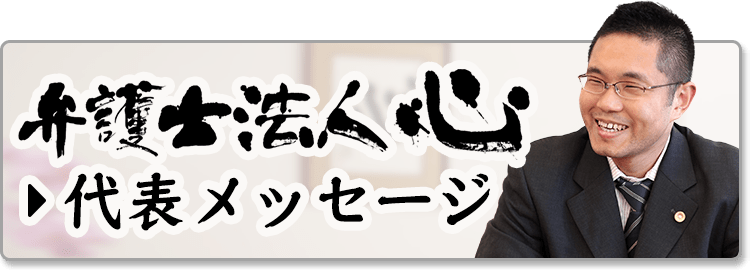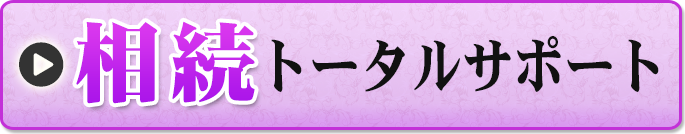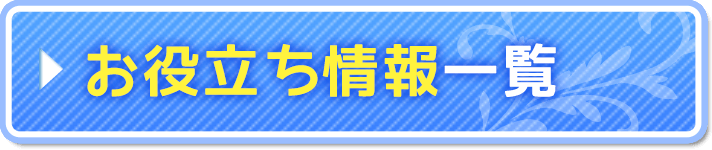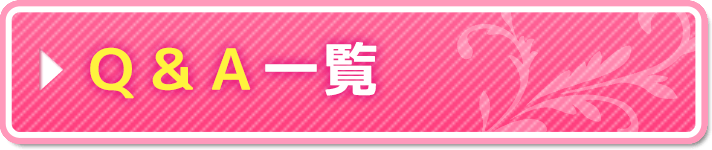遺留分侵害額請求調停の手続き方法やかかる費用
1 遺留分侵害額請求調停の手続き
遺留分侵害額請求調停を提起する場合の手続きについて解説していきます。
⑴ 申立人
遺留分侵害額請求調停を提起することができる人は以下のとおりです。
① 遺留分を侵害された方(兄弟姉妹以外の相続人)
② 遺留分を侵害された方の承継者(相続人、相続分を譲り受けた者)
被相続人の方の兄弟姉妹には、遺留分が無い点には注意が必要です。
また、遺留分侵害額調停は令和元年7月1日以前に被相続人の方が亡くなった場合には申立てを行うことができない点にも気を付けましょう。
⑵ 申立先
遺留分侵害額請求調停を提起する裁判所は以下のとおりです。
① 相手方の住所地の家庭裁判所
② 当事者が合意で定める家庭裁判所
ここでいう「相手方」とは、遺留分を侵害した方を指しています(正確には具体的な計算を行う必要がありますが、簡単な理解としては「遺言書によって財産を受け取った方」というような理解で問題ございません。)。
また、ご自身がお住まいの地域の家庭裁判所に申立てを行えるわけではなく、提起できる裁判所は法律で決まっている点に注意が必要です。
⑶ 申立て費用
申立てを行う際に、家庭裁判所に対して収入印紙の納付と予納郵券(相手方への書類の郵送に使用する切手)の提出を行います。
① 収入印紙1200円
② 予納郵券(各家庭裁判所によって金額が異なります。)
⑷ 必要書類
申立てを行う場合には、以下に記載する書類を家庭裁判所に対して提出する必要があります。
① 申立書 3通
裁判所の定める書式を活用して申立書を作成していきます。
申立書は、相手方に送付される資料になりますので、裁判所用、相手方用、申立人控え用の3通を提出することになります。
この時に提出する遺産目録には、被相続人の遺産を記載していくため、どの財産がどこに所在しているのか等を正確に記載していく必要があります。
② 送達場所等届出書 1通
裁判所の定める書式に送達場所等届出書の書式がありますので、こちらを活用して提出を行います。
③ 進行に関する照会回答書 1通
裁判所の定める書式を活用して照会回答書を作成していきます。
この時に、これまでの交渉経緯等について記載していくため、ご自身に不利な事実の記載を行っていないかの確認が必要です。
心配な点がある場合には、必ず弁護士に確認を取るようにしましょう。
④ 相続人全員の戸籍等謄本(全部事項証明書) 1通
※取得から3か月以内のもの
⑤ 被相続人の出生時から死亡時までの全ての戸籍謄本(全部事項証明書・除籍、改製原戸籍謄本等) 各1通
※取得から3か月以内のもの
⑥ 遺産目録 1通
⑦ (遺産に不動産がある場合)不動産登記事項証明書 各1通
※取得から3か月以内のもの
⑧ 遺言書の写し又は遺言書の検認調書謄本の写し 1通
⑸ 進行について
家庭裁判所に申立てを行った後には、家庭裁判所から期日の指定が行われます。
指定された期日までに、遺留分に関して主張したい点等があれば、事情説明書を作成して、ご自身の主張を書面として提出する必要があります。
また、必要に応じて証拠資料の収集、作成を行う必要があるため、時間が無い方や、どのような証拠を収集する必要があるか分からないという方は、弁護士に相談を行うようにしましょう。
2 費用
遺留分侵害額請求調停では、以下のような費用がかかることがあります。
① 不動産鑑定費用
不動産の評価額を正確に決定するために、不動産鑑定士による評価を行う場合があります。
こちらは、難易度や報酬体系によっても変わってきますが、20万円~70万円程度かかることが多いです。
② 弁護士費用
弁護士に依頼して請求を行う場合、弁護士費用が発生します。
弁護士費用は、事務所によって異なりますが、最低でも40万円程度の報酬が発生し、それに加えて回収した金額に対する何%という形で費用を支払うことになります。
弁護士に依頼する場合には、必ず最低限度の報酬金額と回収した金額に対する何%が報酬となるかを明確に把握するようにしましょう。