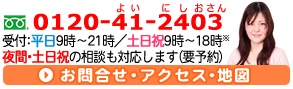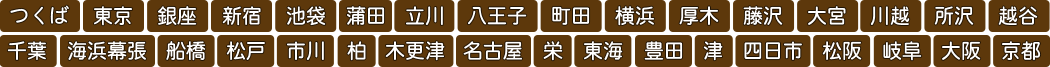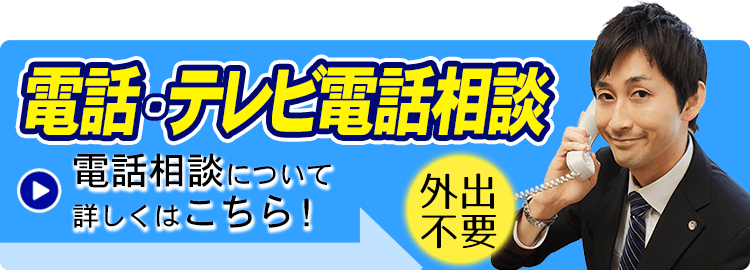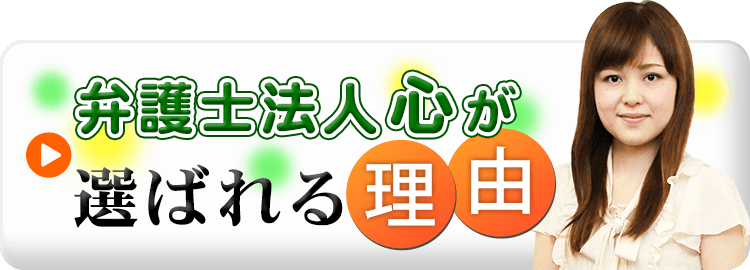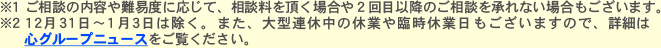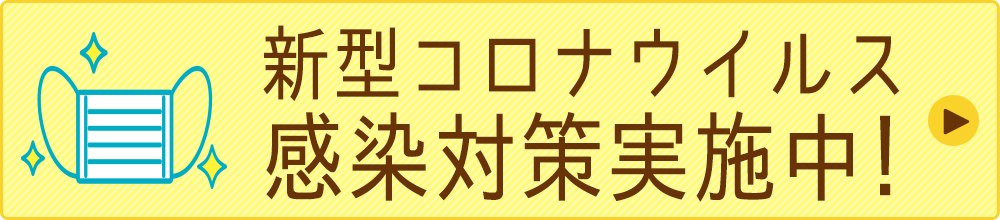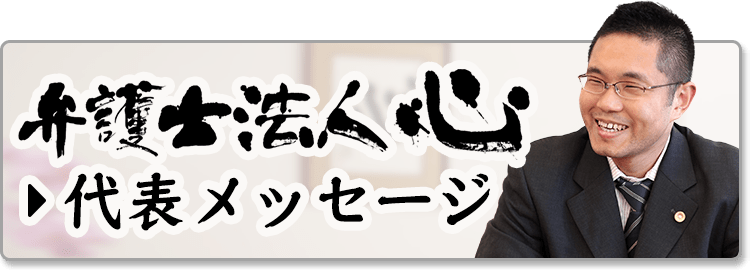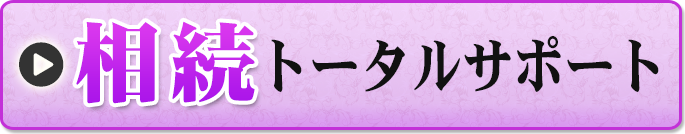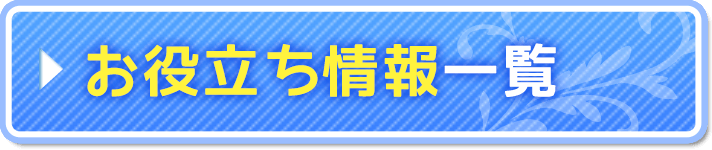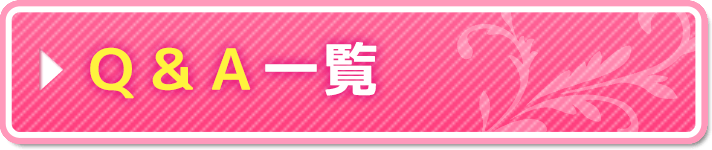債務がある場合の遺留分侵害額請求
1 債務がある場合の具体的な遺留分侵害額の算定について
具体的な遺留分の算定方法については、「遺留分の額から遺留分権利者が相続によって得た財産の価額を控除し、同人が負担すべき相続債務がある場合にはその額を加算して算定する」とされています(最判平成8年11月26日判時1592号66頁)。
この判例は、平成30年の民法改正前のものですが、改正後の民法1046条第2項に反映されています。
そして、遺留分算定の基礎となる財産額については、被相続人が相続開始時において有していた財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とされています(民法1043条第1項)。
この遺留分の基礎となる財産から控除される債務は、被相続人の負担した債務を意味し、契約などの私法上の行為に基づく債務だけでなく、税金や罰金などの公法上の債務も含まれます。
借入金については、金融機関からのものに限られず、個人的な借入れも含め、遺留分の基礎となる財産から控除される債務にあたります。
未払いの家賃や施設利用料についても、遺留分の基礎となる財産から控除される債務にあたります。
これらの調査の方法としては、金融機関や業者との取引履歴を調べたり、亡くなった方の自宅などの生活の本拠となる場所にある書類などをもとに調べたりする方法があります。
2 遺留分算定において控除されない債務
相続財産に関する費用、遺言執行に関する費用、相続税、葬儀費用については、遺留分算定において控除される債務にはあたりません。
3 債務がある場合の遺留分侵害額請求に関わる相談
弁護士法人心では、遺留分などの相続に関するご相談をお受けしております。
遺留分侵害額の請求については、その算定の基準となる計算が非常に複雑になりますので、当事者ではその算定が困難なことがあります。
被相続人に債務があるなどして遺留分侵害額の請求についてお困りの方がいらっしゃいましたら、ご相談いただきたいと思います。