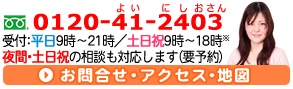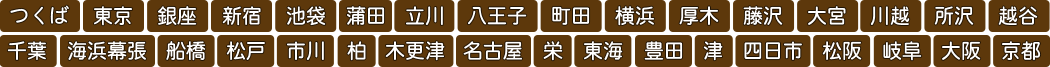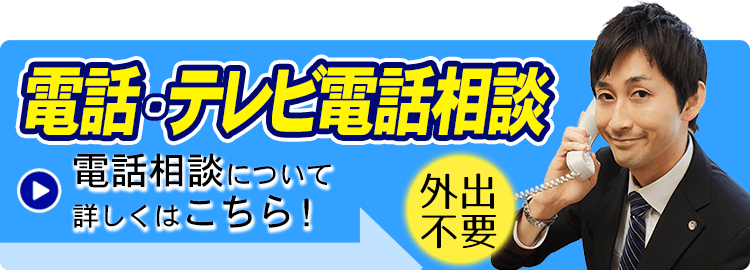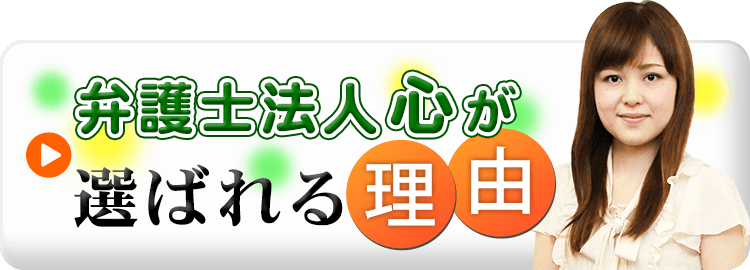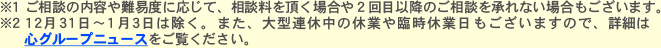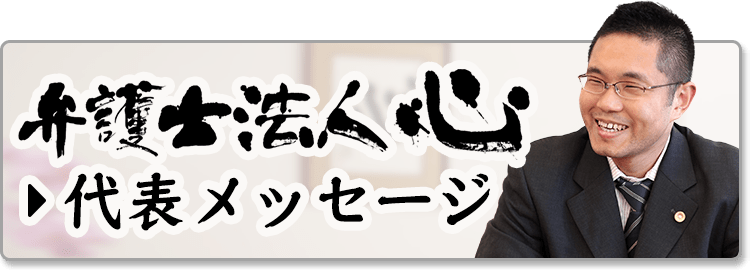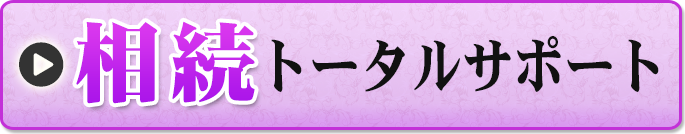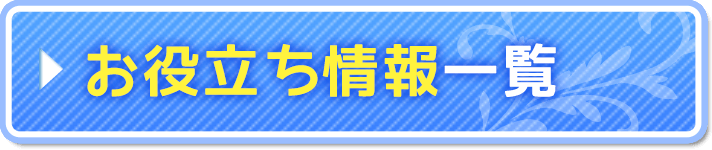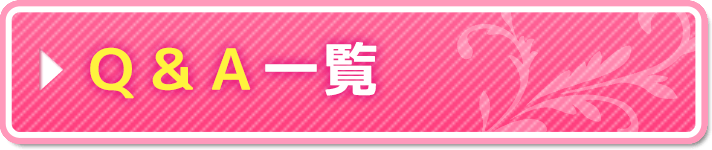遺留分と特別受益
1 遺留分とは
遺留分とは、相続人のうちの一部の方について、相続財産のうち一定の割合を認めるものです。
兄弟姉妹を除く法定相続人は、遺留分侵害額請求をできる場合がありますが、この遺留分侵害額請求ができる期間は法律によって決められています。
2 遺留分権利者は誰なのか
遺留分権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
兄弟姉妹、相続欠格者、廃除された方や相続を放棄した方は遺留分権利者ではありません。
3 遺留分の割合は?
遺留分全体の割合は、直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の3分の1となります。
それ以外の方が相続人である場合は、被相続人の財産の2分の1です。
上記に、それぞれの遺留分権利者の法定相続分の割合を掛けた割合が、それぞれの遺留分権利者の個別的な遺留分になります。
4 特別受益とは
特別受益とは、生前贈与や遺贈によって被相続人から特に利益を得ている相続人がいる場合に、その受けた利益をその相続人の相続分の一部であるとみなす制度をいいます。
この制度は、相続人の間の公平を図るものです。
どのようなものが特別受益に当たるかについては、その贈与の性質や金額によって変わってきます。
また、特別受益は、具体的相続分を算定する際に考慮されるものですが、被相続人が意思表示により、相続分の算定時に特別受益を計算の対象とすることを免除することもできます。
他方、遺留分算定の際にはこのような免除は認められていません。
遺留分は、配偶者、直系尊属、直系卑属が一定額の相続財産を確保できるよう認められた制度であるため、特別受益も遺留分算定の際に考慮する対象となります。
5 遺留分と特別受益の関係
特別受益が問題になるのは、具体的相続分算定の場面です。
具体的相続分を算定する場面というのは、遺産分割によって誰がどの財産を取得するかを決める場面です。
他方、遺留分が問題になるのは、遺言や生前贈与のような相続が開始する前の財産処分によって、最低限の遺産ですらもらえない相続人が出てきた場面です。
全員が最低限の遺産が相続できる場合には、遺留分は問題となりません。
このように、特別受益と遺留分は、その意味合いの働く場面が異なることを押さえておく必要があります。
6 遺留分侵害額の算定方法
民法の改正により、相続人に対する生前贈与の範囲に関する規定の見直しがありました。
改正前の民法では、遺留分の計算上算入される贈与は、①相続開始前の1年間にしたものと、②当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、特段の事情がない限りすべての期間の贈与が算入されることとなっていました。
また、特別受益の扱いは、1年以上前の贈与も含めて原則としてすべて加算されていました。
特別受益とは、被相続人の生前に、共同相続人の中の一人が婚姻、養子縁組のためや生計の資本として受けた贈与のことをいいます。
対して、改正後は、相続人に対する贈与は、特別受益に該当する贈与で、かつ、原則として相続開始前の10年間にされたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額へ算入することになっています。
7 特別受益は遺留分算定の際に考慮される
特別受益は、遺産分割の際に各相続人が具体的な取り分を決める際に考慮する事項です。
上にも少し書きましたが、被相続人が、相続開始までに、特別受益を遺産分割の場へ持ち戻す必要がないことを、明示または黙示に意思表示をしていれば、原則として特別受益を取り分として考慮しなくてもよいことになっています。
具体的相続分を算定する際に、特別受益の持戻しが免除されることはありますが、遺留分算定の際には持戻し免除の有無にかかわらず、すべての特別受益が、遺留分算定の基礎財産に入れられることになります。
特別受益の持戻しが問題となるのは、具体的相続分を算定する場面だけということになります。
8 遺留分や特別受益に関するトラブルの解決はお任せください
特別受益と遺留分は、問題となる場面が異なりますが、関連する部分もあるため混乱しやすいところです。
また、相続に関する法改正があったことにより、遺留分の計算方法についても様々な影響が生じます。
弁護士法人心では、相続案件を集中的に取り扱う相続チームを設け、対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。