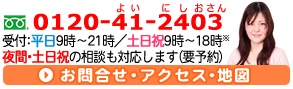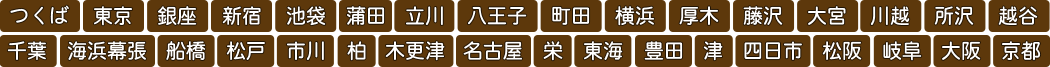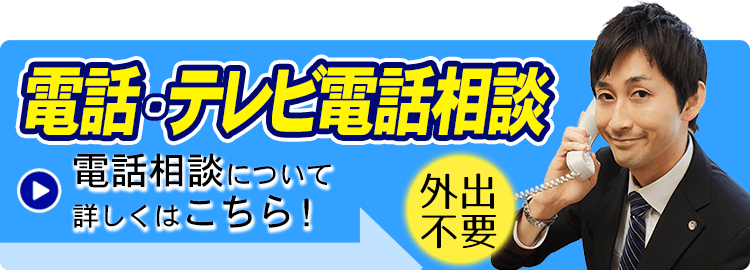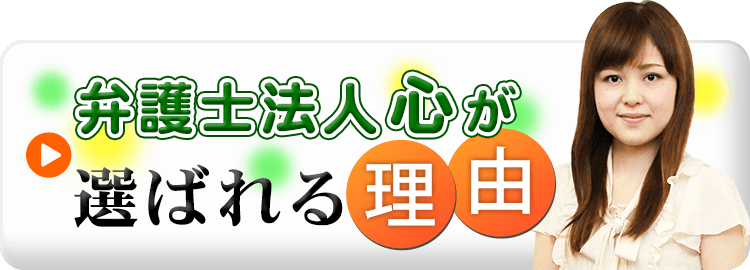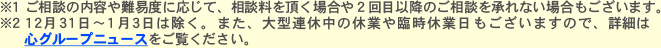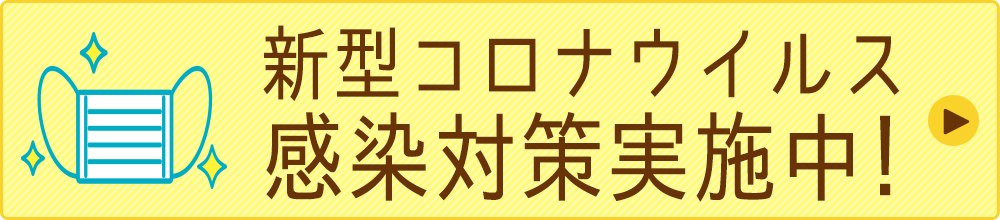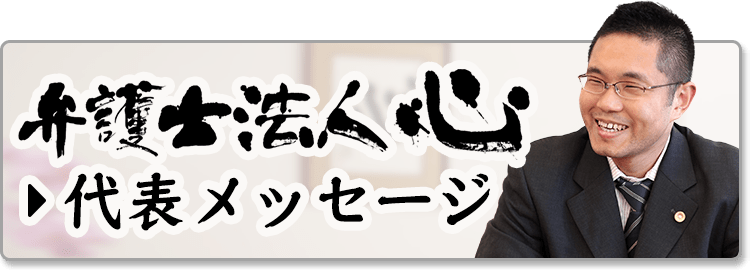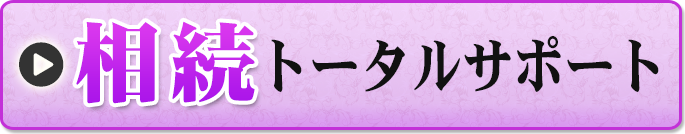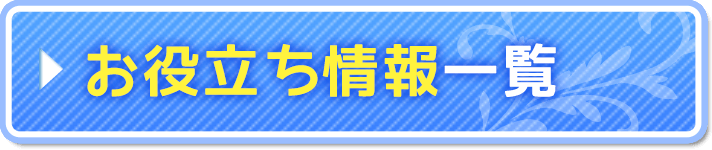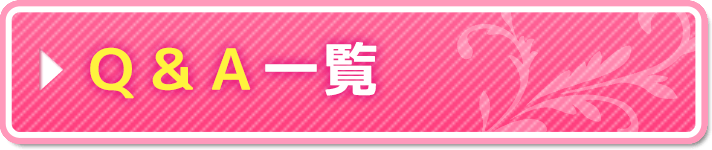遺留分を請求するための手続き
1 時効が完成する前に遺留分を請求する意思を相手方に伝える
遺留分の請求に決まった方法はないため、遺留分を侵害している相手方に対し、口頭で遺留分を請求することも可能です。
しかし、遺留分の請求は相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈を知った時から1年が経過すると、請求できなくなってしまいます。
そのため、口頭で遺留分の請求を行っただけで、そのまま放置してしまうと、後になって相手方から「1年間が経過したから遺留分は請求できない」と主張されてしまい、請求を行ったと証明できないおそれがあります。
また、書面で遺留分の請求をしたとしても、そのような内容の書面を送ったという証拠がないと、やはり1年間が経過したという相手の主張に反論することが難しい場合があります。
そこで、遺留分の請求を行ったという証拠を残しておくため、遺留分の請求は内容証明郵便で行うべきです。
ただし、遺留分の請求をしたことが明確である書面を送らなければ、証拠として機能しない場合もあります。
また、相手方によっては書面を受け取らないことで「1年以内に請求されていない」と主張する可能性もあるため、対応方法については相続案件を集中的に取り扱っている弁護士に相談することをおすすめします。
2 通知を送った後の手続き
- ⑴ 相手との話合い
-
遺留分の請求を行っても、最初から裁判所で決着をつけるということにはなりません。
まずは話合いで合意ができないかを探ることが多く、合意ができればそこで遺留分の問題は解決します。
ただし、後になって「そんな合意はしてない」と主張する人が現れると紛争の蒸し返しになってしまうため、どのような合意をしたのかについて書面で残しておく必要があります。
- ⑵ 調停
-
当事者の話合いで解決できなかった場合は、裁判所で調停を申し立てて解決することになります。
調停は、調停委員を交えて当事者が合意できる案を探っていく手続きですが、あくまでも話合いですので、お互いの合意が得られない場合には、調停は終了します。
- ⑶ 訴訟
-
調停でも解決できなかった場合は、訴訟を提起することになります。
ここまで来てしまうと、すでに長期間紛争が継続していることになり、精神的にも負担が大きくなってしまうかと思います。
当事者間だけの話合いでは、感情論などで議論が紛糾し、建設的な話合いができず、結局訴訟にまでいってしまうという場合があります。
そのため、弁護士に相談されるのであれば、できるだけ早い段階で相談するとよいかと思います。
3 遺留分の請求を考えている方は弁護士へご相談ください
遺留分の請求は、遺留分の複雑な計算や、専門的な知識が必要です。
また、遺留分を請求する手続きを間違えると、1年間という期限によって、遺留分を請求できなくなるという事態もあり得ます。
そのような事態を防ぐため、遺留分の請求を考えている方は、できるだけ早い段階で弁護士へ相談することをおすすめします。